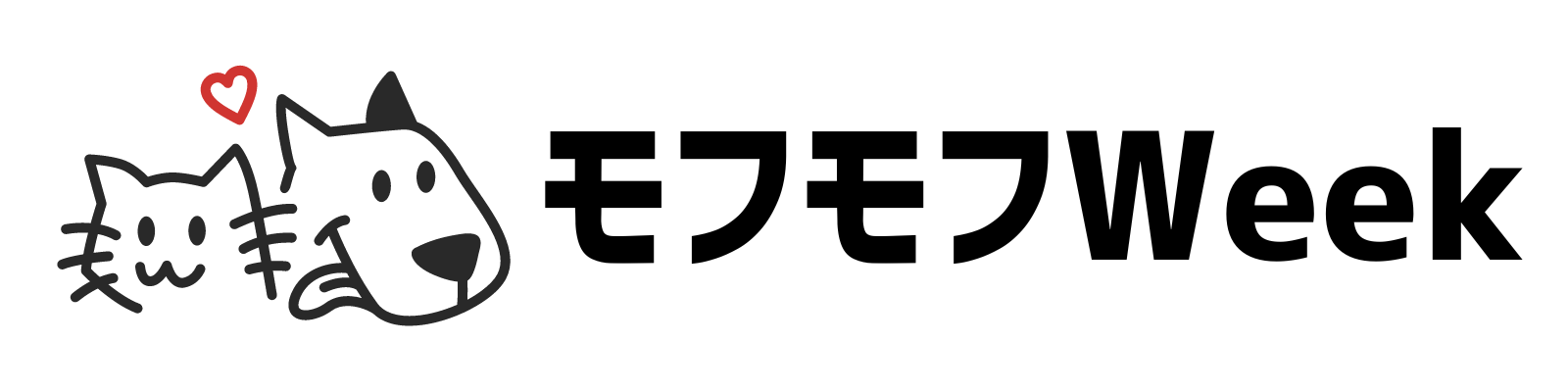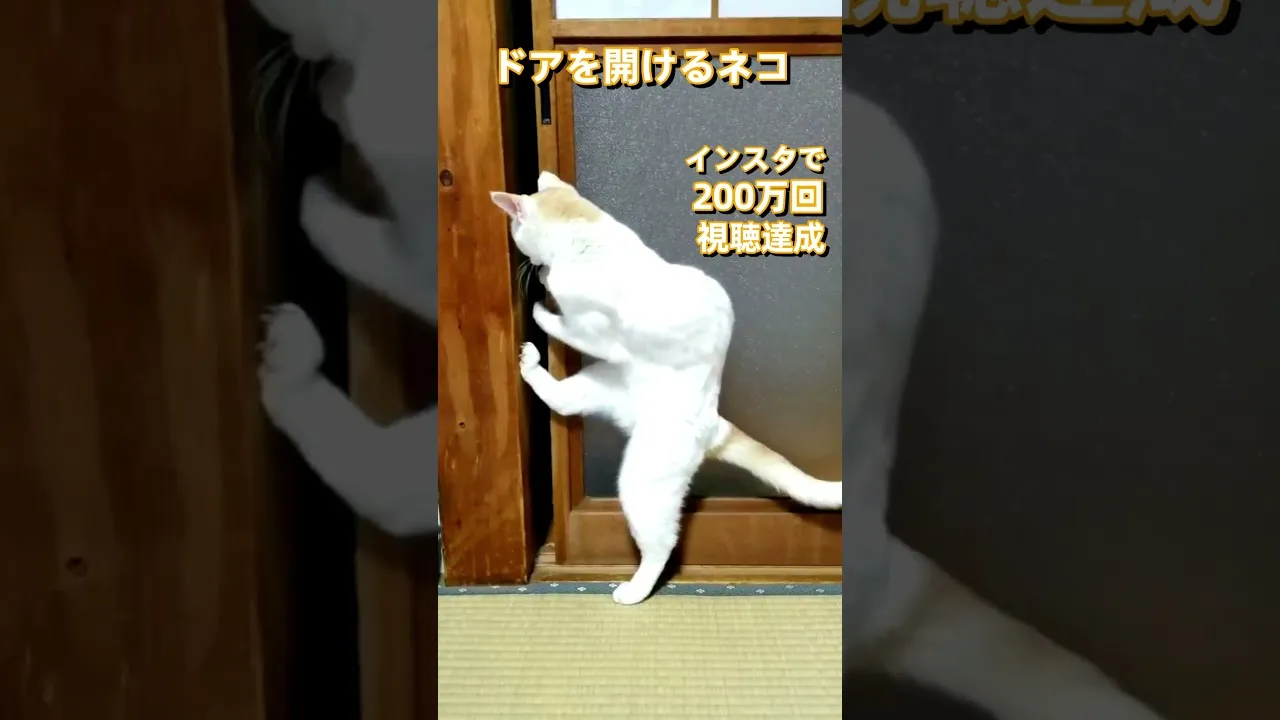一般的に「ニャー」と鳴くと知られている猫。実はその鳴き声にも色んな種類があることを知っていますか?
猫を飼っている人のなかには、さまざまなバリエーションの鳴き声を聞いたことがある人も多いでしょう。猫は意図的に鳴き声を使い分けて、自分の気持ちを飼い主さんに伝えようとしているのです。
そこで今回は、猫の鳴き声とそれぞれの持つ意味を解説します♪ また、猫の鳴き声が止まないという悩みを抱えている人に向けたおすすめの対処法も紹介。ぜひ参考にしてくださいね!
猫を飼っている人のなかには、さまざまなバリエーションの鳴き声を聞いたことがある人も多いでしょう。猫は意図的に鳴き声を使い分けて、自分の気持ちを飼い主さんに伝えようとしているのです。
そこで今回は、猫の鳴き声とそれぞれの持つ意味を解説します♪ また、猫の鳴き声が止まないという悩みを抱えている人に向けたおすすめの対処法も紹介。ぜひ参考にしてくださいね!
猫はなぜ鳴く?

そもそも、猫はなぜ鳴くのでしょうか?
実は、子猫のときや発情期を除いて猫は本来あまり鳴きません。なぜなら、単独行動をとることが多い猫にとって、鳴き声は自分の居場所を敵や獲物に知らせるというデメリットになってしまうからです。
猫同士のコミュニケーションは基本的に仕草や姿勢、表情やしっぽの動きをつかって行われます。つまり、猫同士のやり取りに鳴き声は必要なく、人とコミュニケーションを取るために猫は鳴いているのです!
飼い主さんに何かを伝えたいとき、仕草や表情よりも声を出すのが一番かんたんで確実ですよね。では、そんな猫たちが一体どんな鳴き声で、何を伝えようとしているのかを紹介していきます♪
実は、子猫のときや発情期を除いて猫は本来あまり鳴きません。なぜなら、単独行動をとることが多い猫にとって、鳴き声は自分の居場所を敵や獲物に知らせるというデメリットになってしまうからです。
猫同士のコミュニケーションは基本的に仕草や姿勢、表情やしっぽの動きをつかって行われます。つまり、猫同士のやり取りに鳴き声は必要なく、人とコミュニケーションを取るために猫は鳴いているのです!
飼い主さんに何かを伝えたいとき、仕草や表情よりも声を出すのが一番かんたんで確実ですよね。では、そんな猫たちが一体どんな鳴き声で、何を伝えようとしているのかを紹介していきます♪
猫の鳴き声10種類と意味を解説!

意外と種類豊富な猫の鳴き声。その種類は声のトーンや長さで聞き分けることができますよ♪ 本記事では全部で10種類の鳴き声を紹介します!?
飼い主に要求するときは「ニャーン」「ニャオ」
「ニャーン」や「ニャオ」と繰り返し鳴くときは、何かを要求していたり、甘えたりしていることが多いです。
例えばお腹がすいているときなら「ごはんちょうだい」、トイレの近くで鳴いているときは「トイレ掃除をお願い!」、ドアの近くなら「ここを開けて~」、機嫌がいいときは「遊んで!」など、同じ鳴き方でもその理由はさまざま。
甘えたいときほど声のトーンは高くなり、要求が強いほど大きく長い鳴き声になると言われています♪ この鳴き声を聞いたときは、タイミングや状況を見て何を求めているのかを考えてみましょう◎
例えばお腹がすいているときなら「ごはんちょうだい」、トイレの近くで鳴いているときは「トイレ掃除をお願い!」、ドアの近くなら「ここを開けて~」、機嫌がいいときは「遊んで!」など、同じ鳴き方でもその理由はさまざま。
甘えたいときほど声のトーンは高くなり、要求が強いほど大きく長い鳴き声になると言われています♪ この鳴き声を聞いたときは、タイミングや状況を見て何を求めているのかを考えてみましょう◎
挨拶をするときは短い「ニャッ」という鳴き声
軽く「ニャッ」と鳴くときは、挨拶をしていることがほとんど。飼い主さんやその家族など、よく知っている人を見たときや、名前を呼ばれたときなどに鳴くことが多いです。また、同居の猫同士による挨拶もこの鳴き方。いずれも好意的な意味を表しています。
おいしくてご機嫌なとき「ウニャウニャ」
ごはんが美味しいときに「ウニャウニャ」「ウマウマ」と鳴くことがあります。すべての猫に当てはまるわけではないものの、まるで「うまい、うまい」と言いながら食べているようにも見えることから、ネット上で動画が話題になることも♪
これは子猫が母乳を飲みながら、親猫に満足感を伝えるために声を出していたことの名残だとも言われていますよ。
これは子猫が母乳を飲みながら、親猫に満足感を伝えるために声を出していたことの名残だとも言われていますよ。
一安心したときの「フゥー」
緊張がほぐれたときや、落ち着いたときに出るのが「フゥー」という鳴き声。まるで人間のため息のように、鼻からフゥーと息を吐くような音を出します。猫自身がリラックスできた証といってもいいでしょう。
リラックスしているときの「ゴロゴロ」
機嫌が良いときに出るのが「ゴロゴロ」という音。喉の奥で鳴らすような音で、リラックスしている状態を表しています。とくに撫でられているときや、飼い主さんの近くに寄り添っているときに出すことが多いです。
ただ、どの猫も必ずしも「ゴロゴロ」と喉を鳴らすわけではなく、警戒心が強い猫や親離れが出来ている自立心の高い猫などの場合「ゴロゴロ」と言わないケースもあります。また、「ゴロゴロ」と鳴っているものの、人間には聞き取りづらいほど小さな音を発している場合も。
ただ、どの猫も必ずしも「ゴロゴロ」と喉を鳴らすわけではなく、警戒心が強い猫や親離れが出来ている自立心の高い猫などの場合「ゴロゴロ」と言わないケースもあります。また、「ゴロゴロ」と鳴っているものの、人間には聞き取りづらいほど小さな音を発している場合も。
痛いとき、やめてほしいときの「ギャア」
人にしっぽを踏まれたり、何か痛いことがあったり、やめてほしいことがあったりしたときは大きな声で「ギャア」と鳴きます。自然と出た悲鳴のような声で、もしかしたらけがをしている可能性もあるため、この鳴き声を聞いたら念のためにボディチェックをするようにしましょう。
威嚇するときは「シャー!」「ン―」「ウー」
ほかの猫や見知らぬ人などに対して強い警戒心を抱いているときに出るのが「シャー!」という鳴き声。仕草としても毛を逆立てたり、耳を立てたりして相手を威嚇します。
また、口を閉じて低く唸るように「ン―」「ウー」と鳴くときも威嚇の合図。猫は縄張り意識が強いため、この鳴き声が出たときは自分のテリトリーから他者を追い払おうとしていることが多いです。そのため無理に近づいたりはせず、距離をとって静かに見守るようにしましょう。
また、口を閉じて低く唸るように「ン―」「ウー」と鳴くときも威嚇の合図。猫は縄張り意識が強いため、この鳴き声が出たときは自分のテリトリーから他者を追い払おうとしていることが多いです。そのため無理に近づいたりはせず、距離をとって静かに見守るようにしましょう。
興奮したときに出す「カカカカ」
遊んでいるときや獲物を見つけたときなど、興奮しているときに出す独特な鳴き声が「カカカカ」というもの。これは「クラッキング」や「チャタリング」などと呼ばれ、猫の狩猟本能からくる鳴き声です。
実は、ライオンやトラなどの大型猫科動物にはできない猫特有の鳴き声なんですよ♪ 窓の外に飛んでいる鳥や、届かない場所を飛んでいる虫など、捕まえたいのに届かないというもどかしい気持ちを表しているといわれています。
実は、ライオンやトラなどの大型猫科動物にはできない猫特有の鳴き声なんですよ♪ 窓の外に飛んでいる鳥や、届かない場所を飛んでいる虫など、捕まえたいのに届かないというもどかしい気持ちを表しているといわれています。
発情期のときに出す「アオーン」
異性の猫を呼んだり、その声に応えたりするときは遠吠えのように「アオーン」と鳴きます。猫は生後半年から1年ほどの間に初めて発情期を迎えます。そこで、避妊・去勢手術をしていない猫は外に向かって「アオーン」とかなり大きな声で鳴くのです。季節としては、春や夏の温かい時期が多く、昼夜問わず鳴き続けることもあります。
子猫が親猫に甘えるときのサイレントニャー
口を開いて「ニャー」と鳴く動きをしているものの、発生がない状態を「サイレントニャー」といいます。これは主に子猫が親猫に甘えるときの鳴き方で、人間には聞こえない高周波の音を出しているとも言われています。
この「サイレントニャー」を飼い主さんにしている場合は主に愛情表現や、構ってほしい、さみしいなどの気持ちを表しています。この仕草を見たら優しく撫でたり、抱っこしてあげたりなど、スキンシップをしてあげましょう。
この「サイレントニャー」を飼い主さんにしている場合は主に愛情表現や、構ってほしい、さみしいなどの気持ちを表しています。この仕草を見たら優しく撫でたり、抱っこしてあげたりなど、スキンシップをしてあげましょう。
病気のサイン?注意するべき猫の鳴き声

鳴き声は猫の気持ちや状態を表す重要なサイン。もし、以下のような鳴き声をした場合は、注意して様子を観察しましょう。
かすれた声で鳴いている
甘えるときに出す「サイレントニャー」と似ていますが、もし普段はよく鳴いている猫が急に発声しなくなったり、声を出したいのにかすれて出ていなかったりしたら注意が必要かもしれません。
考えられる要因はいくつかあります。まずはシンプルに喉が乾燥している可能性。その場合は、いつでも飲めるように清潔な水を用意したり、ウェットタイプのフードやおやつを与えたりすることがおすすめです。
考えられる要因はいくつかあります。まずはシンプルに喉が乾燥している可能性。その場合は、いつでも飲めるように清潔な水を用意したり、ウェットタイプのフードやおやつを与えたりすることがおすすめです。
もし、かすれた声で鳴くだけでなく、くしゃみや鼻水なども併発している場合は猫風邪の可能性も。室内で飼っている場合はそこまで感染症のリスクは高くありませんが、飼い主さんが外猫を触った手で撫でていたり、手にウイルスがついたまま触ってしまったりすると感染してしまうこともあるかもしれません。
くしゃみや鼻水などの症状がない場合は、鳴きすぎで炎症を起こしている場合や、咽頭炎など治療の必要な疾患である可能性もあります。少しでも異変を感じたら早めに動物病院を受診するようにしましょう。
くしゃみや鼻水などの症状がない場合は、鳴きすぎで炎症を起こしている場合や、咽頭炎など治療の必要な疾患である可能性もあります。少しでも異変を感じたら早めに動物病院を受診するようにしましょう。
元気がなさそうに「ナーナー」と鳴く
猫が「ナーナー」と元気がなさそうに鳴いている場合は、疲れていたり、体力が低下していたりします。高齢の場合は関節痛の痛みを感じている可能性も。継続して「ナーナー」と鳴き続けている場合は、病院に連れて行ってあげるのが良いかもしれません。
猫の鳴き声の対処法

猫のかわいい鳴き声ですが、ずっと止まらなかったり、夜寝ているときに鳴き声で目が覚めてしまったりして悩んでいる人もいるのではないでしょうか? また、住んでいる場所によってはご近所トラブルが心配になる人もいるかもしれません。
とはいえ、猫にも鳴く理由があるのでむやみにやめさせることは難しい……。そこで、さまざまなケースに合わせたおすすめの対処法を紹介します。
とはいえ、猫にも鳴く理由があるのでむやみにやめさせることは難しい……。そこで、さまざまなケースに合わせたおすすめの対処法を紹介します。
ご飯の量を見直す
猫はまとまった量を一度に食べるという習慣がありません。そのため、お腹がすいたと鳴いている場合は、容器が空っぽになっていないかチェックをしましょう。長時間ごはんが補充されていなくて、鳴いて知らせている場合がありますよ。
また、ご飯の量が少なくないかを確認する必要があるかも。体の大きさにあった量になっているか、今一度見直してみるのもいいかもしれません。
また、ご飯の量が少なくないかを確認する必要があるかも。体の大きさにあった量になっているか、今一度見直してみるのもいいかもしれません。
こまめにトイレを掃除する
トイレの近くで「ニャーン」や「ニャオ」と鳴いている場合は「トイレを綺麗に掃除して」というサイン。そのときは、排泄するたびに猫砂を取り除いたり、定期的に砂の取り換えをしたりすることをおすすめします。汚れたトイレを嫌がる綺麗好きな猫もいるので、こまめに掃除をして清潔に保つことで要求鳴きが減るかもしれません。
もし、定期的なトイレ掃除が難しい場合は自動で掃除をしてくれる猫トイレがおすすめです♪
もし、定期的なトイレ掃除が難しい場合は自動で掃除をしてくれる猫トイレがおすすめです♪
miruto
¥46,800 (2025/05/15 19:41時点 | Amazon調べ)
時には応えないことも大切
猫が構ってほしい、遊んでほしいと要求しているときは、毎日短時間でも猫との時間を作ったり、休日にたっぷり遊んであげたりすることが大切です。
ただ、要求を満たしても鳴き声が止まらない場合は、鳴けば何か出てくると思っている可能性も……。ここは心を鬼にして、鳴いても返事をしない、応じないという態度をとることも大切です。遊ぶときは思いっきり遊んであげて、寝る時間になったら放っておくなど、生活にメリハリをつけることで「鳴いても必ずいいことが起こるわけではない」と理解し、鳴き癖を防止することができますよ◎
ただ、要求を満たしても鳴き声が止まらない場合は、鳴けば何か出てくると思っている可能性も……。ここは心を鬼にして、鳴いても返事をしない、応じないという態度をとることも大切です。遊ぶときは思いっきり遊んであげて、寝る時間になったら放っておくなど、生活にメリハリをつけることで「鳴いても必ずいいことが起こるわけではない」と理解し、鳴き癖を防止することができますよ◎
キャットタワーなどで環境の改善を
鳴き癖がなかなかやまない場合は、強いストレスを抱えている可能性があります。特に夜鳴きはストレスや欲求不満のサインかも。その場合は猫が暮らしやすいような環境に変えてあげることがおすすめです。
猫は高いところを登ったり、歩いたりすることが大好き。キャットウォークやキャットタワーを設置してより快適な環境にしてあげましょう♪
猫は高いところを登ったり、歩いたりすることが大好き。キャットウォークやキャットタワーを設置してより快適な環境にしてあげましょう♪
去勢・避妊手術をする
発情期は昼夜問わず、大きな声で鳴くようになるので、飼い主さんの睡眠を妨げてしまうこともあるかもしれません。ただ、これは本能のため鳴かないようにコントロールすることは難しい。飼い猫に出産を望まないのであれば、早めに去勢または避妊手術をして発情期にならないようにすることがおすすめです。
まとめ

もともと鳴き声を出さずにコミュニケーションを取っていた猫。人に何かを伝えるために鳴くようになったのですから、そのメッセージはきっちりと理解してあげられるようになりたいですよね。
もし、何を伝えているのかわからない場合はぜひこちらの記事を参考にしてください♪ また、過度な要求鳴きに困った場合もそれぞれの状況を観察しながら対応して、飼い主さんにとっても、猫にとっても快適な生活を送れるようにしましょう◎
モフモフweekでは、役に立つ雑学から癒される動画まで、さまざまな情報を更新中♪ 猫好きにぜひ挑戦してほしいクイズも出題しているので、この機会にぜひご覧ください!
もし、何を伝えているのかわからない場合はぜひこちらの記事を参考にしてください♪ また、過度な要求鳴きに困った場合もそれぞれの状況を観察しながら対応して、飼い主さんにとっても、猫にとっても快適な生活を送れるようにしましょう◎
モフモフweekでは、役に立つ雑学から癒される動画まで、さまざまな情報を更新中♪ 猫好きにぜひ挑戦してほしいクイズも出題しているので、この機会にぜひご覧ください!